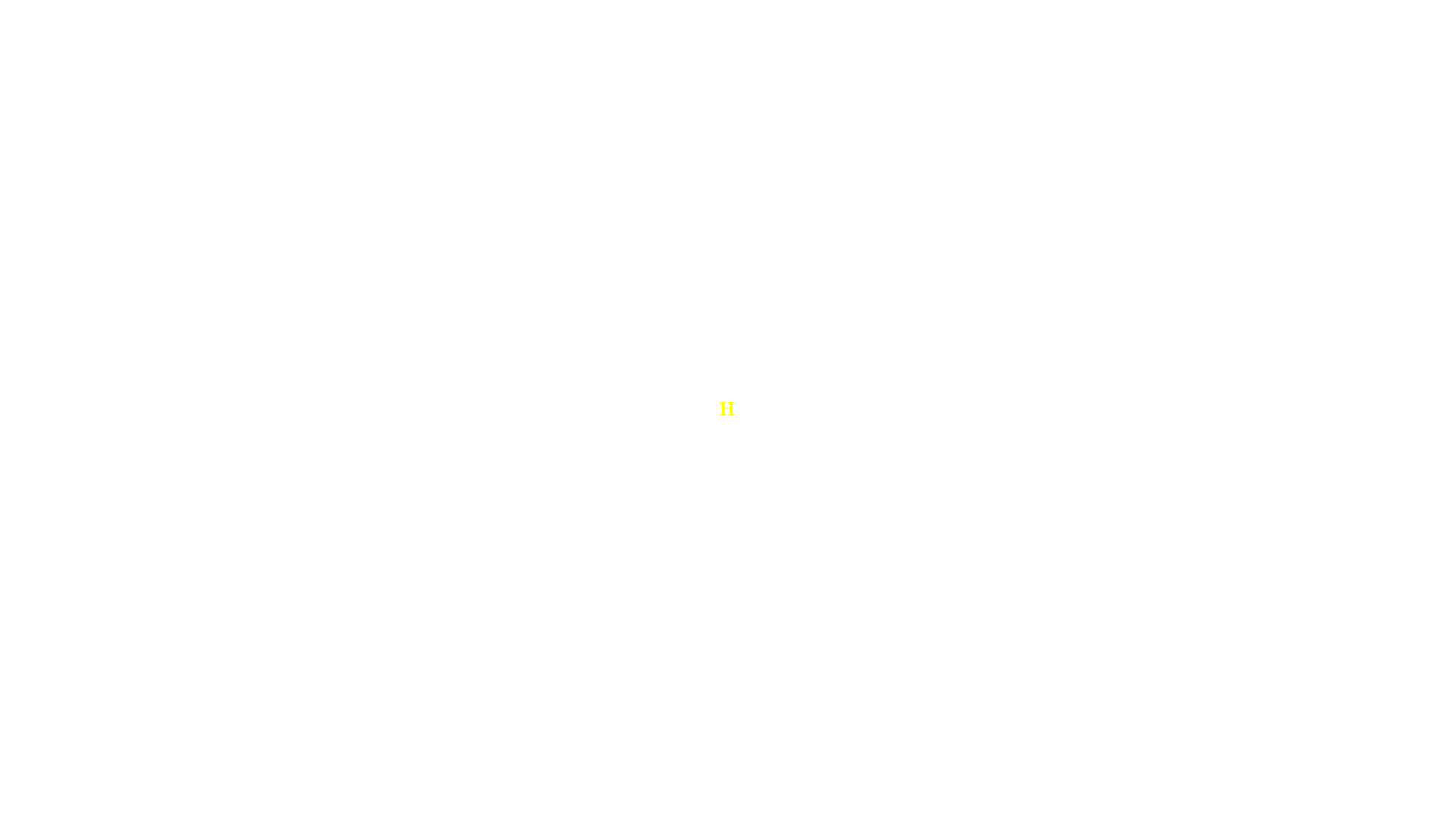この章は来る世界に向けて「お勧めのストーリー」としてAKがKeen-Area Newsで紹介した記事を「人類への教科書」として掲載する物である。もちろんはるとが承認済である。


Human Textbooks
2020TheNewEarthAtravelreport【1】浜辺の出来事
1.浜辺の出来事
動画版に関しては私の環境では非常に明瞭にセリフが聞き取れるのだが、スピーカーの特性によっては「聞き取りずらい」らしい。
特にスマフォでの視聴はBGMだけが強調され、セリフが聞こえないのでご容赦願いたい。
初期の動画に関してはほぼそのような状態であるが、すでにアップしたものはYoutebeでは修正ができないということを、ご理解いただきたい。
特にスマフォでの視聴はBGMだけが強調され、セリフが聞こえないのでご容赦願いたい。
初期の動画に関してはほぼそのような状態であるが、すでにアップしたものはYoutebeでは修正ができないということを、ご理解いただきたい。
6月のある日、僕たちは猛暑の中にいた。
焼け付くような日射しだったが、僕は数人の友人と海にいたため、暑さは気にならなかった。
むしろ、その暑さが、僕らが度々海水に身を浸し、自由な時間を楽しむよう誘ってくれた。
ストレスのない休日。
世界はOKに見えたし、それ以外の見方をすることに何の興味もなかった。
友人たちの方に目をやると、彼らは水の中で、見るからに楽しげに遊んでいた。
「人生は素晴らしい!」それからひそかに思った。
「なぜ、いつもこんな風じゃないのだろう?」
僕は目を閉じて背を反らせた。
「太陽よ照りつけておくれ。燦々と頼むよ!」しばらくして目を開けた。
僕の体を優しくなでてくれる涼やかな風に、僕は微笑んでいた。
体を起こすと軽く目眩がした。
あったはずの水筒がない。
僕のバッグもだ!それから友人たちもいなくなっていることに気付いた。
「大した冗談だな」そう思って立ち上がり、あたりを見回すと、友人どころか、誰もビーチにいないことがだんだんわかってきた。
僕たちは、このビーチが旅行者に知られていないから気に入っていたのだが、それでも奇妙なことだ。
30分前にバナナの皮を捨てたゴミ箱もなくなっている。
僕の周りは緑色だらけになっていた!僕は夢を見ているのか?これは現実か?
太陽は、先ほどと同じくやはり照りつけているし、海もそこにある。
泳ぐために海水に入った。
少しの間混乱を忘れたいという思いに駆られたのだ。
ところが、海の中から浜辺や島を見て、僕はショックを受けた。
僕はどこにいるのだろう??山々の稜線は確認できるが、以前とはまったく違って見えるのだ。
いつもの、乾ききったような夏の景色が、今はすべて緑色なのだ。
その島に何世紀も無かったはずの森が見える。
僕は過去にいるの?タイムトラベルしたのだろうか?夢に違いない。でも、何もかもあまりにも現実的だ!
僕はゆっくりと泳いで浜辺に戻った。
水は腰の高さしかなかったが、砂が僕のお腹をくすぐるまで、泳いだ。
僕はそこでワニのように横たわり、動かないまま、辺りを目で窺っていた。
自分が何を探しているのかさえわからない。
何か、何かあるはずだ。僕が今見ているものに説明がつくものが。
それは僕の混乱した頭をすっきりさせてくれるだろう。
気分が悪いわけでも、怖いわけでもない。
僕の感覚は完全に研ぎ澄まされている。
僕はゆっくり立ち上がり、僕がタオルを置いた場所に歩いて行く。
僕は用心しながらそれを拾い上げる。
何かが起きてくれることを期待しながら。
けれども何も起こらない。
いつもタオルが拾われるときのようにタオルは拾われた。
僕はタオルを肩に掛け、駐車場に歩いて行く。
だんだん、これが悪ふざけじゃないことがわかってきたが、それでもそこに友人たちがいることを願った。
そこに駐車場がないことを僕にはなかなか受け入れられなかった。
その場所はあるのだが、植物が生い茂っており、その中央には焚き火台がある。
そばに行って灰に指を突っ込むと火傷した。
ついさっきまで誰かがここにいたに違いない。
燃え殻がまだ赤い。
「こんにちは?誰かここにいますか?コーンーニーチーワー!」ためらいながら声をかけてから、今度は精一杯声を張り上げる。
「コーーーンーーーニーーーチーーーワーーー!!!」僕の声に驚いた鳥が、木々の間から数羽飛び立っただけだ。
「ここで何が起きているのだろう?」声に出して自分に聞いてみる。
すると、僕の質問に答えるように、カモメが頭上でうるさく鳴いた。
まるで僕の知らない何かを知っているかのように。
見上げると、カモメが島の中心に飛んで行くのが見えた。
何の考えもないまま、足が勝手に歩き始め、僕はカモメを追う。
カモメが視界から消え、僕は駐車場から通り道に出る。
1時間前に通った道も、やり前と違っている。
同じ道だが、僕の周りの何もかもが緑に染まっているのだ。
数百メートル歩いてから気付いたのだが、ただ緑が濃くなっているだけではなく、周りの植物がすべて実をつけている。
熟した果実、未熟な果実がたくさん実っていて、どれもみんな食べられるものだ!僕は、ブラックベリーの茂みのところで立ち止まった。
よく熟れた果実がたわわに実っている。
その藪の中央から、イチジクの木が突き出ている。
僕は喉が渇いていたのを思い出し、水筒もなくしていたので、いくつかつまんで食べた。
ああ、なんてうまいんだ!ジュースが僕の喉をなだめるように下りていく。
少しの間、僕は他のことを忘れていられた。
イチジクがこんなにジューシーだとは知らなかった。
イチジクは甘くてジューシーだ。
2019-12-28 01:01:51